2010年11月22日
”従業員にとっての働きがい”を実現したStory①㈱Plan・Do・See《I am one of the customers》
 活力溢れる企業への注目度が高まっている
活力溢れる企業への注目度が高まっている
・厳しい経済環境下でも、組織として一体感を持ち、社員一人一人がイキイキ働いている。そんな活力溢れる企業への注目度が、ますます高まっています。
・なぜ、彼らは活力に溢れているのか?その背後にある仕組み、経営者や社員の想いに迫ることで、これからの時代を勝ち抜いていく企業に求められる要素について追求していきたいと思います。
・当ブログでは、シリーズ投稿として今後5回に分けて、特に注目度の高い企業にスポットを当てていきます。ネタ元となっている資料は、先日発売された書籍【日本でいちばん働きがいのある会社】。このシリーズを通じて、どんな可能性のある会社と新たに巡り会えるのか。今から楽しみです。
・シリーズ第1回目となる今回ご紹介する会社は、【株式会社Plan・Do・See】(以下、PDS)。レストランウェディング業界の先駆けとして業績を伸ばし続けており、同書籍では【連帯感】で最高評価を獲得しています。
 会社概要&直近の業績推移(東京商工リサーチより)
会社概要&直近の業績推移(東京商工リサーチより)
会社名 株式会社Plan・Do・See
創業年 1993年4月
代表者 野田豊 ※1968年生まれ、42才
従業員 350名
主業種 バンケット(披露宴の企画運営)、レストラン&バーの運営
売上値 2009年 10,146,067(千円)
2008年 8,087,377
2007年 7,793,837
 レストランウェディング業界って?
レストランウェディング業界って?
・同社と競合関係にある企業の多くは、実は同時期(1990年代前半~)に創業されています(ウェディング業界市場売上ランキングより)。”レストランウェディング”という言葉が流行り出したのも、この頃から。バブル経済崩壊後に生まれた、比較的新しいビジネスモデルであることが見えてきます。
・それまでの結婚式と言えば、親戚から会社関係の人たちまで大勢集め、豪華な食事と盛大なセレモニー。世間体や格を重んじる色が強いものでした。必然的に、挙式にかかる金額は跳ね上がります。また、こうした準備は全てブライダル業者に一任(丸投げ)する傾向が強く、業者が多額のマージンを得る余地を与えることになり、結果として業界全体が高コスト体質(∵高い利ザヤに胡坐をかいていた)に陥っていたようです。サービス内容も画一的で、工夫のないものに。。。
・しかし、バブル崩壊により、事態は一変します。高コストに対して厳しい目が向けられると共に、消費者の意識は、「世間体や格式≒見栄よりも、本当に親しい仲間達と充足する機会を共有したい」という欠乏に向かっていきました。こうした外圧状況の変化に、既存のブライダル業者は応えられなくなっていった。
・そこにビジネスチャンスを見出したのが、PDSであったと言えます。
『ブライダル業界も、原点回帰の時代に入った。日本には世界に誇れる”おもてなし”文化がある。日本の”おもてなし”文化を海外に輸出したいと思っている』
・サービス業は、まさに人材力が成功の鍵を握ります。一人一人の社員が持つ力を最大限引き出すために、同社が積み重ねてきた秘策とは。。。?ヒントは、《I am one of the customers》という言葉にあるようです。
 《I am one of the customers》あってこその未来
《I am one of the customers》あってこその未来
PDSの社員のよりどころとなっているのが、PDSのミッション《StyleあるSceneをServiceすること》、ビジョン《世界で日本のおもてなしをスタンダードにすること》、バリュー(行動規範)《I am one of the customers》である。
《I am one of the customers》は、自分だったらうれしいと思えることをしよう、自分だったら欲しいなあと思える商品を提供しよう、ということだ。
「おそらく今は、全社員が、誰かに喜んでもらいたいことが好きな人たちです。基本的にこの会社に、お金持ちになりたいとか、昇進して偉くなりたい、ということが第一目的で入社する人は、まずいません。いわばPDSの社員は皆、この《I am one of the customers》を、喜びをもって日々実践している人たちだといってもいいでしょう」
会社だから数字も大事だ。実際のところ、経営陣から売上の数字を上げろと言われれば、非常に抗しがたいものがあるので、売上げを上げることだけに走ってしまうということも起きる。
「ただ、売上拡大のみに走ると、短期的に良く、未来に強い会社かというとそんなことはないです。やはり《I am one of the customers》が大事であり、これだけは譲れないといつも社員に話しています」
・同社の強みは、《I am one of the customers》を始めとする企業理念・目標・方針の共有を徹底的に行っている点にあります。一切の序列関係を廃し、風通しの良い空間の中で、採用~研修~普段の会話に至るあらゆる場において、社長自ら率先して社員とのコミュニケーションを図り、自らの想いを様々な手法を駆使して何度も繰り返し言葉化して伝えていく。そうすることで、会社として向かうべき方向と社員一人一人の想いは一つに重なり、組織は”血の通った”ものになっていきます。例えば、
 採用パンフレットはメンバーをサポートするためのツール
採用パンフレットはメンバーをサポートするためのツール
普通、採用パンフレットは、就職活動をする人に向けてつくるものである。しかしPDSでは、あえて社員向けにつくっている。
「就職説明会で話すときも、学生さんを口説こうとするのではなくて、見ている社員をモチベートしよう、サポートしようと思って話しているんです」
それでいいなあと思ってもらえる人しか、PDSの事業に合っていないということを見極める手段にもなるそうだが、採用を通してもう一度メンバーに、何をするために自分がPDSに入ったのかという原点を思い起こしてもらおうという狙いがあるという。
「ですから会社説明会には、どんなに時間的金銭的コストがかかってもアルバイトを含む全従業員に、必ず1回は参加してもらいます。そのために東京出張もさせます。交通費だけで年間1,000万円近くかかりますが、これで全従業員がモチベートされ、勇気とやる気が湧いてくるなら安いものだと考えています」
 The Plan・Do・See Recipe=日々の行動、充足規範集
The Plan・Do・See Recipe=日々の行動、充足規範集
Episode1:「愛されよう」 編~素直に感謝を言葉に、他人の成功を喜ぶ~
Episode2:「楽しもう」 編~いつも「あったらいいな」を考える~
Episode3:「やさしくなろう」編~どんなアイデアも殺さない~
Episode4:「強くなろう」 編~スピード感を大切に、抱え込みは悪~
・それ以外にも、【ランチ手当】制度を導入して社員同士の交流を後押ししたり、福利厚生制度の一つとして【ファミリー懇親会】を3ヶ月に1回開催、社員の家族同士でも交流を図っていこうとするなど、社内外問わず”想いを共有する場作り”には事欠きません。
・こうして《I am one of the customers》への収束力を高め続けられる背景には、同社に訪れた一つの逆境も影響しているようです。
新たに店舗をオープンしたり、またときにクローズしたりしながら、夢に向かって前進してきたPDS。しかし2002年に大きな転機が訪れる。
「それまで目標にしてきた上場をやめることにしたのです。実は、お金で人をモチベートするのをやめようと決めたのもこの頃です」
それまでは、よくあるベンチャーのお決まりとして、上場を考え、上場することで人材や資本、信用が得られて、次のステージに行けると考えていた。けれども上場を意識したあたりから、PDSはおかしくなり始めていた。
「いつのまにかお客様の笑顔より、会社を大きくすることのほうが大事だというスタッフも出始め、ベクトルがばらばらになっていました」
上場をやめようと決断したことで、上場に期待し、拡大や成長などが目的となっていた社員が次々とやめる事態に陥ったようです。しかしそこでくじけることなく、より一層”想いを一つにする”方向へと舵を切れたからこそ、現在のPDSがあると言えそうです。
『うまくいかない時、苦しい時は、《I am one of the customers》に立ち戻って考えてみればいい。そうすれば必ずうまくいく』
 置かれた環境を貫く 闘争圧力を把握せよ
置かれた環境を貫く 闘争圧力を把握せよ
とりわけ重要なのは、次の点である。
置かれた環境を貫く闘争圧力が、(個体を構成する各機能であれ、あるいは集団を構成する各個体であれ)最末端まで貫通した圧力として働いているからこそ、その圧力に適応する最先端機能へと(各機能や各個体が)収束し、全体が統合されるのであって、この圧力がなければ、最先端機能も統合機能として働かない。また、最末端まで貫通した圧力の存在を捨象して、統合機能の真の姿が見える訳もない。
改めて、るいネットのこの投稿が思い出されます。
PDSは、これまでの成功体験・ノウハウからより普遍的な言葉=認識を抽出し、人材コンサルティング等の新規事業へ打って出始めています。獲得してきた認識の商品化を目指すPDS、これからも注目してきたい企業の一つです。
byひろ 
- posted by taka at : 10:00 | コメント (2件) | トラックバック (0)


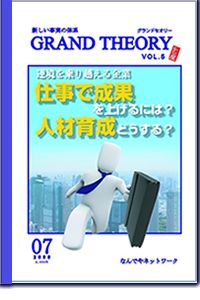
コメント
市場を延命させるために、どこかでバブルを引き起こし破綻させる。今度はそれを救済するために、借金が増大する・・・まさに借金経済ですね(×。×)
実質的に大企業に有利な優遇措置(≒特権)を得た大企業は、政治家・官僚・マスコミ同様に「暴走する特権階級」のひとつ、と言えそうですね。
でも、一体「特権」って何なんでしょうか。
政府の予算(税金・借金)を自由に使うことができる権限、と言えそうですが、自由に使えるわりには(だからこそ)、頭を使わずに湯水のように市場に吸い取られている感じですね。
コメントする